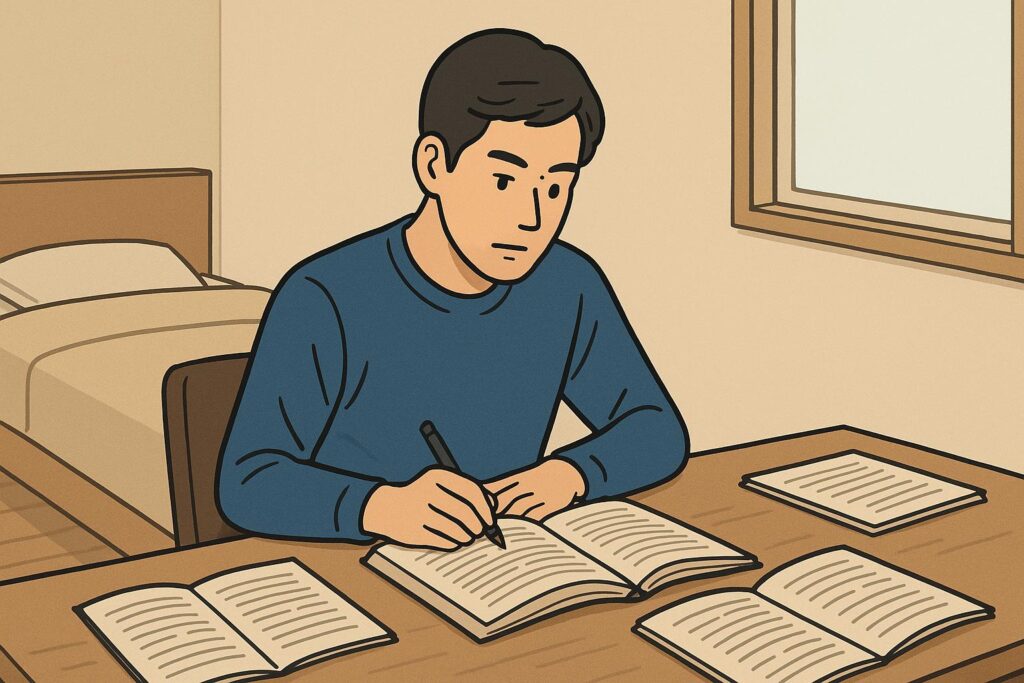
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回も「独身一人暮らし男性のためだけの税理士試験勉強法」という、
超ニッチなテーマでお届けします。
前回の記事「独身一人暮らし男性のためだけの税理士試験合格法」が思いのほか多く読まれ、
「で、実際どうやって勉強してたの?」とご質問いただくことが増えました。
今回は、特に私が「法人税法」に合格したときの勉強スタイルを、完全公開します。
法人税法の試験は「理論+計算」のハイブリッド
まず前提として、
税理士試験の法人税法は「理論」と「計算」がほぼ半分ずつ出題されます。
どちらも避けて通れません。
以前の記事で、合格には年間1000時間の勉強が必要と書きました。
1日平均3.5時間。
これを365日続ける生活です。
私が通っていたのはTAC。
この記事は、その中で編み出した戦術と習慣についての備忘録でもあります。
通常期(9月〜4月)の1日の流れ
通常期は授業の進度に合わせて淡々とこなしていく時期です。
私の基本ルールは「授業までに1単元を3周する」ことでした。
まず、勉強のスタートは理論から。
次の授業でミニテストがある論点だけを対象に、
何も見ずに書けるまでひたすら書いて覚えます。
翌日には忘れているので、
再度同じように書いて覚え直す。
それを繰り返すことで、
1週間後にも思い出せるようになります。
理論が済んだら計算に着手。
1授業分の範囲を3周するため、
毎日少しずつ計画的に解いていきます。
無理せず、しかし確実に。
直前期(5月〜7月)の戦い方
直前期になると、やることは明確です。
答練(模試のようなもの)の出題範囲しか勉強しません。
ここでありがちなのが「本試験が近いから全部やりたい」という焦り。
ですが私は出題される範囲のみに絞り、答練に全集中しました。
理論も答練の出題論点だけを対象に、相変わらず書いて覚える。
計算も補助問題や答練の計算パートだけを使い、こちらも毎週3周を守ってループ。
無駄な範囲に手を出さず、「出題される部分だけを、確実に覚える」を徹底しました。
超直前期(試験日前の2〜3週間)の過ごし方
超直前期は、もう演習もないので自学習のみ。
私は理論マスター(理論のまとめテキスト)をひたすら読み込みました。
文字通り、1ページ目から最後まで読み、
終わったらまた1ページ目から。
これを空き時間すべてで行います。
通勤時間も昼休みも、理論マスターとともに。
計算は、5月以降に受けた答練や補助問題だけを再び解いていく。
つまりこれが4周目。
これにより、脳がその論点に反射的に反応するようになります。
理論の勉強で大切にしたこと
理論の勉強は「書いて覚える」に尽きます。
音読でも読書でもありません。
書くことで記憶に刻まれるのです。
「どこまでやればいいの?」という質問には、
「覚えるまで」と答えるしかありません。
そもそも、覚えきれていない状態で次に進むのは無意味。
また、「読んで覚える」というのは、
超直前期のような限られた時間にだけ有効です。
通常期〜直前期はとにかく書いて身体で覚える。
計算の勉強で意識したこと
計算についても、「全部3周」がマイルールです。
問題集・答練・補助問題すべて。
正直、1周や2周で解けるようになる論点もあります。
でも繰り返す理由は「スピードを上げるため」。
税理士試験は上位10%が合格します。
つまり、正確さだけでなく処理速度も試される。
そのためには手が勝手に動くくらいまで繰り返すしかありません。
成果と、1度の失敗
この勉強法をして、私は1回法人税法に落ちました。
正直、相当へこみました。
ですが、得点は目に見えて伸びており、
次年度にまったく同じ勉強法で臨んだ結果、無事合格しました。
間違いなく「勝ちパターン」だったと確信しています。
最後に:できるならやる、できないなら撤退
私が今回紹介した方法は、ストイックで極端です。
でも「上位10%の合格者」になるには、
このくらいの変人になる必要があると本気で思っています。
受験予備校の休憩スペースで、
やる気のないおじさんがたむろしている光景を見たことはありませんか?
「記念受験だから~」と自分を甘やかす20年目の先輩はいませんか?
そんな環境に引きずられてはいけません。
人生を変えたいなら、普通の生活を捨てる必要があります。
受かりたいなら、今日から生活を変えましょう。
できないなら、撤退もまた一つの戦略です。
お問い合わせはコチラ→https://tktk-tax.com/contact/